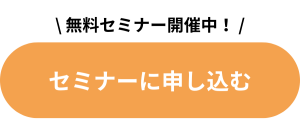定量データが揃わない初期検討でも、投資判断や企画の優先順位は待ってくれません。そんなとき、短時間で“桁感”を掴み、仮説立案の精度を一段上げる思考法が フェルミ推定 です。限られた情報を「人口 × 利用率 × 単価 × 頻度」などに因数分解し、透明性のある前提と計算で市場規模を素早く見積もれます。
本ガイドでは、フェルミ推定の基本構造(トップダウン/ボトムアップ)と前提の置き方、感度分析の要点を、実務の手順に沿って解説します。
フェルミ推定とは
定義と目的
フェルミ推定(Fermi Estimation)とは、限られた情報からおおよその数量や市場規模を論理的に導き出す推定手法です。
シカゴ大学の物理学者エンリコ・フェルミが「シカゴ市内のピアノ調律師の数」を概算した逸話に由来し、「複雑な現象を分解し、仮定を置いて構築する」ことに特徴があります。
データが不足する初期段階でも、「おおまかな桁感を把握する」ことで、投資判断やリサーチ優先度を決められる点が実務的価値です。
なぜ市場規模推定に使われるのか
市場規模を推定する際、信頼できる統計データが常に存在するとは限りません。
フェルミ推定は、「人口 × 利用率 × 単価 × 頻度」などの因数分解を通じて、データが欠けていても論理的に数値を導けるため、 新規事業・商品企画・営業資料・ピッチなどで頻繁に活用されます。
特に、早期段階の検証では「仮説思考」と「数量感の整合性」を担保する指標として重宝されます。
フェルミ推定の基本構造
トップダウンとボトムアップ
フェルミ推定は大きく2つのアプローチで構築します:
- ・トップダウン型:国全体など大きな母集団から段階的に絞り込む方法(例:日本人口 → 成人 → コーヒー飲用者 → コンビニ利用者)。
- ・ボトムアップ型:個別単位(店舗・ユーザーなど)から積み上げて推定する方法(例:1店舗あたり販売数 × 店舗数)。
どちらの方法も、「計算の透明性」と「前提の一貫性」が最も重要です。
市場規模 = 人口 × 利用率 × 単価 × 頻度
実務で多用される式が次のような単純構造です:
市場規模(円)= 対象人口 × 利用率 × 購入単価 × 購入頻度
この式をベースに、仮定値を置いて計算すれば、ほぼすべての消費市場を定量化できます。
「対象人口」と「頻度」を誤ると一桁違う結果になるため、ここがフェルミ推定の肝です。
前提条件の置き方
誰が・どのくらい・いくら払うか
フェルミ推定の精度は、前提条件の設定で決まります。
次の4要素を論理的に置くことが基本です:
- 1.人口(母集団):対象市場の最大範囲。例:成人男性、日本の就業者、スマホ保有者など。
- 2.利用率(行動率):実際にその商品・サービスを使う人の割合。
- 3.単価:1回あたりまたは年間あたりの平均支出額。
- 4.頻度:購入や利用の回数。
人口・利用率・単価・頻度の設定例
| 要素 | コンビニコーヒー市場を例にした設定 | 根拠の取り方 |
| 人口 | 日本の成人約1億人中、都市圏でのコンビニ利用者7,000万人 | 公的統計+生活者調査 |
| 利用率 | そのうち週1回以上購入する人:30% | 自社アンケートまたは感覚値 |
| 単価 | 平均150円 | 店頭価格 |
| 頻度 | 月に8回 | 平均的出勤日数から仮定 |
計算プロセス
要素分解 → 仮定値設定 → 概算
フェルミ推定では、以下の3ステップで市場規模を求めます:
- 1,要素分解:構成要素(人口、利用率、単価、頻度)を整理
- 2.仮定値設定:信頼できる一次データや推定値を代入
- 3.概算:四則演算で市場全体を導出
感度分析でレンジを確認する
フェルミ推定の目的は「正確さ」ではなく「誤差の範囲を知ること」です。
各前提を±10〜20%動かした場合の市場規模の変化を試算し、“推定レンジ(下限〜上限)”を明示することで、信頼性が高まります。
例:コンビニコーヒー市場=6,000〜8,000億円レンジ
→ 投資検討時の「桁感」は十分に示せる。
例題:コンビニコーヒーの市場規模推定
前提
| 項目 | 仮定値 | 根拠 |
| 全国コンビニ店舗数 | 約56,000店 | 日本フランチャイズ協会 2024 |
| 1店舗あたり平均販売数 | 150杯/日 | 各社IR資料・店舗観察 |
| 平均単価 | 150円 | 税抜換算 |
| 営業日 | 365日 | 通年営業を想定 |
結果と示唆
市場規模 = 56,000 × 150 × 150 × 365 = 約4,600億円
この結果から、単価×頻度での感度が高い(価格改定や販売促進の影響を受けやすい)ことがわかります。
また、1社あたりシェア20%なら売上は約920億円規模と見積もられ、
競合比較や販売戦略の指標として実務的に活用できます。
応用:オンライン学習市場の推定
ターゲットと前提設定
| 項目 | 仮定値 | 根拠 |
| 対象人口 | 社会人約6,000万人 | 総務省統計 |
| 利用率 | オンライン学習経験者20% | 各種調査平均 |
| 年間支出額 | 平均25,000円 | Udemy等プラットフォームの平均価格 |
| 頻度 | 年1回利用 | 学期単位の受講を想定 |
計算式と感度分析
市場規模 = 6,000万 × 0.2 × 25,000 × 1 = 3,000億円
感度分析:
- ・利用率25%の場合 → 3,750億円
- ・支出額20,000円の場合 → 2,400億円
このように、仮定を変動させることで市場レンジ(約2,400〜3,750億円)が把握でき、
新規事業の投資可否判断に使えます。
よくあるミスと注意点
分母・分子の不整合/重複カウント
「人口×利用率×頻度」を掛ける際に、同一利用者を二重カウントしてしまうミスがよくあります。
特にチャネル別・商品別を合算する場合は、利用者重複を避けましょう。
「年」↔「月」換算忘れ
単価を月単位、頻度を年単位にしてしまうなどの単位不整合が誤差を生みます。
フェルミ推定では、すべての前提を同一期間(例:年間ベース)に揃えるのが原則です。
推定結果の活かし方
仮説立案と企画精度の向上
フェルミ推定は「市場が小さい」ことを示すためではなく、次の検証アクションを導くためのツールです。
おおまかな桁感を得たうえで、次に行うべきは:
- ・定量調査で母集団の実態を検証
- ・仮定の中で感度が高かった項目に焦点を当てる
スライド化の基本構成(前提→式→結果→示唆)
実務報告や提案書では、以下の順に整理すると説得力が高まります:
- 1.前提条件(仮定値と根拠)
- 2.式の構造(市場規模 = A×B×C×D)
- 3.計算結果(下限〜上限)
- 4.解釈と示唆(どの要素が支配的か)
まとめ
フェルミ推定の価値と限界
フェルミ推定は、「不確実な環境でも合理的に考える」ための思考技術です。
短時間で桁感を得ることができ、企画・戦略・投資判断の初期段階に極めて有効です。
一方で、前提の妥当性次第で誤差が大きくなるため、“根拠を明示した仮定”が信頼性を左右します。
定量調査とのハイブリッド運用
フェルミ推定で得た概算値を、後続フェーズで定量調査(アンケート・購買データ)と照合することで、 より正確な市場規模モデルを構築できます。
「まずフェルミで仮説を置き、次に実データで検証する」流れが、データドリブンな企画の基本です。
デコムでは、もっと学びたい人に向けて様々なイベントやセミナーを開催しています。
是非、この機会にご参加ください。