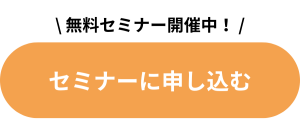競合戦略とは何か?
競合戦略とは、同じ業界や類似の製品・サービスを提供する他社(競合)の動向を把握し、自社が市場で優位に立つための道筋を描くための戦略です。
競合を「敵」と見なすのではなく、競合の強みや弱みを分析し、自社の差別化やポジショニングを最適化するための材料として活用します。
競争戦略では、主に以下の3つの方針が挙げられます:
- ・コスト・リーダーシップ戦略(価格競争力)
- ・差別化戦略(独自の価値提供)
- ・集中戦略(特定市場に特化)
このような枠組みをもとに、自社に最適な戦略を導き出すには、まずは競合の戦略や施策を正確に把握することが出発点です。
競合企業の戦略を調べる方法(実践編)
基本的な情報収集方法
競合の戦略は、次のような方法で間接的に把握ができます。
- ・企業の公式サイトやIR情報:新製品発表、経営方針、成長戦略を把握できます。特にIR資料には、競合がどの分野を重視しているかが明確に記載されていることがあります。
- ・プレスリリース・業界ニュース:戦略的提携やM&Aなどの動向を追えます。業界内でのポジション変更や提携の背景を読み解くと、長期的な意図も見えてきます。
- ・採用ページや求人広告:新規事業や強化領域のヒントになります。求める人材のスキルや職種から、どの分野へ注力しているかを推測できます。
- ・展示会・セミナー登壇内容:重点施策や今後の方向性が語られることがあります。業界全体の動向とともに、競合が打ち出す差別化ポイントが浮き彫りになります。
デジタルツールを使った分析
競合のWeb施策やユーザー行動を把握するには、ツール活用が有効です。
- ・SimilarWeb、SEMrush、Ahrefs:競合サイトのトラフィック源やSEO/広告施策を分析するツールです。流入元や上位ページを見ることで、ユーザー獲得の導線や戦略的コンテンツが把握できます。
- ・Googleトレンド、Keyword Planner:検索ボリュームの推移から注目テーマを読み解きます。市場の関心や季節性の変動も分析でき、タイミングを見た施策に活用可能です。
- ・Sensor Tower、App Annie:アプリダウンロード数やランキング情報から、競合のリリース頻度やアップデート内容など、プロダクト戦略のスピード感が読み取れます。
これらを活用することで、競合の集客戦略やターゲット層の傾向が見えてきます。無料版でも十分に参考情報が得られるため、まずは試してみましょう。
顧客の声から逆算する
競合製品に関する「ユーザーの声」は、重要なヒントを与えてくれます。
- ・口コミサイト(価格.com、Amazonレビューなど)
- ・SNS投稿、YouTubeレビュー
- ・クチコミ分析ツール(User Local、BuzzSpreaderなど)
ポジティブ・ネガティブの両面から、競合の「評価されている点」と「不満点」を把握すれば、自社が補完できるニーズが見つかります。特に不満の声は、自社にとっての差別化や参入余地のある機会領域を示してくれます。
競合分析フレームワーク
競合を深く理解するには、以下の分析フレームワークを活用しましょう。
ポジショニングマップ
自社と競合を2軸(例:価格×品質)で可視化することで、市場内での立ち位置や空白領域(ブルー・オーシャン)を発見できます。視覚的に把握できるため、社内の共通認識づくりや戦略会議の資料としても有効です。
SWOT分析(競合視点含む)
- ・自社・競合それぞれの強み(Strength)・弱み(Weakness)
- ・外部環境の機会(Opportunity)・脅威(Threat)
上記を競合と比較することで、戦略の方向性が明確になり、自社だけが持つ「武器」や「リスク要因」が浮き彫りになります。
4P分析による比較
- ・Product(製品)
- ・Price(価格)
- ・Place(販路)
- ・Promotion(販促)
これらの観点で自社と競合を比較し、自社が突出すべきポイントを見出します。特定の「P」で差別化できれば、他の領域でも優位性を築く足がかりになります。
戦略キャンバス(ブルー・オーシャン戦略)
競合との価値提供要素(項目ごと)を横軸に並べ、優劣や重視度をグラフ化することで、差別化の可視化と「独自性」を設計できます。市場の常識を疑い、「捨てる価値・高める価値」を再定義するための強力なツールです。
戦略立案への活用方法
競合の戦略を調査、分析を行った後は戦略立案に活用しましょう。
差別化戦略の立案
競合と同質化しないためには、顧客が「選びたくなる理由」を構築する必要があります。機能・デザイン・体験・ブランドなどの面で、競合にはない価値を明確に打ち出しましょう。
価格戦略の検討
競合との価格比較だけでなく、「顧客が得られる価値に見合った価格か?」という視点で設計することが重要です。価格以外の要因(安心・サポート・限定性など)で付加価値を訴求できれば、価格競争を避けることも可能です。
マーケティング戦略への反映
調査結果をもとに、ターゲットの見直し、広告メッセージの改善、販路の再検討を行いましょう。特に、競合が手薄なチャネルや訴求ポイントを狙うことで、効果的な顧客獲得が可能になります。
継続的な競合モニタリング
私達だけでなく、競合も変化し続けます。一度の分析だけで満足せず、継続的な観察と適応を行っていきましょう。
定期的な情報更新
- ・3ヶ月〜半年に1回、競合サイトやSNS、業界動向を定期チェックしましょう。タイミングを逃さずに自社の施策へ取り入れることで、素早い対応が可能になります。
- ・社内で「競合ウォッチチーム」を設けるのも有効です。日常的にアンテナを張る人材を明確にすることで、情報収集の質とスピードが上がります。
早期警戒システムの構築
- ・競合のリリースやニュースに即時対応する体制を整えましょう。特に新商品の発表や価格改定などは、即座に影響を受ける可能性があるため、迅速な検知が重要です。
- ・Googleアラートやニュースレター購読で最新情報をキャッチしましょう。自動通知を活用することで、見落としのない情報網を構築できます。
戦略の見直しと修正
環境や競合の変化に応じて、自社の戦略も柔軟に見直しましょう。定期的な戦略レビューを実施し、PDCAサイクルを回すことが肝要です。見直しの際には、数値データだけでなく、現場の声や顧客フィードバックも反映させると実効性が高まります。
実践事例とケーススタディ
競合戦略は理論だけではなく、実際の成功例や失敗例から学ぶことが最も実践的です。ここでは、業種を問わず役立つ2つの成功事例と2つの失敗パターンを具体的に紹介します。
成功事例の紹介
-
BtoB SaaS企業のケース:絞り込みによる差別化
競合が多数の機能を盛り込んだ「総合型ソフト」を展開する中、その企業はあえて機能数を絞り、ユーザーインターフェース(UI)とユーザー体験(UX)に特化した製品を開発。結果として、特定業務に特化したユーザー層から支持を得てシェアを拡大しました。
競合の弱点(複雑さ)に着目し、「使いやすさ」という差別化ポイントを打ち出した例です。ニーズが明確な顧客層を深掘りした戦略が功を奏しました。
-
飲食チェーン店のケース:高価格でも選ばれる理由を設計
そのお店は、競合よりも価格が高いメニュー構成にもかかわらず、「国産素材の産地明示」や「徹底した衛生管理」といった安心・安全への投資を徹底。これによりファミリー層や高齢者などの信頼を獲得し、高価格でも高回転率を実現しました。
価格競争に巻き込まれず、「信頼価値」を武器にして競合と棲み分けを図った例です。ブランドポジショニングを強化することで、リピーター獲得にも成功しています。
失敗パターンと注意点
-
模倣だけで終わった戦略:競合のコピーは逆効果になることも
ある企業は、競合が導入したサブスクリプションモデルに追随。しかし、顧客との接点設計やサービス体制が整っていなかったため、継続率が低く、むしろブランドイメージを損なう結果になりました。模倣は短期的な戦術としては有効でも、戦略としては「自社らしさ」との整合性が必要です。
「何を真似るか」よりも「なぜそれが競合にとって有効だったか」を理解しなければ、単なる後追いで終わってしまいます。
-
戦略の自己満足化:競合分析をしても顧客が見えていない
競合分析を丁寧に行った企業が、独自性を出すことにこだわりすぎ、ユーザーの利便性を無視した複雑な仕様や表現に走ってしまったケースです。「競合と違うことをする=顧客にとって良いこと」、とは限りません。
顧客の視点に立ち、実際の使いやすさ・わかりやすさに落とし込めなければ、分析結果も空回りします。競合との差別化はあくまで“顧客にとっての価値”であるべきです。
このように、成功例からは「どのように差別化し、市場を獲得したか」、失敗例からは「分析や施策が的を外すとどのようなリスクがあるか」が明確に学べます。競合戦略は、調査だけでなく、それをどう解釈し、顧客と接続できるかが本質であると心得ましょう。
まとめ
競合戦略は、相手の真似をすることではなく、相手を理解して、自社の強みを活かすための戦略的思考です。以下のステップを踏めば、実務に活かせる競合戦略を立てることができます。
- 1.競合の施策を多角的に調査する
- 2.フレームワークで構造的に分析する
- 3.自社の強みを明確にして差別化を図る
- 4.継続的に情報を更新し、変化に柔軟に対応する
競合を知ることは、自社を知ることにもつながります。戦略的な競合分析を通じて、より確かな勝ち筋を描きましょう。
デコムでは、もっと学びたい人に向けて様々なイベントやセミナーを開催しています。
是非、この機会にご参加ください。