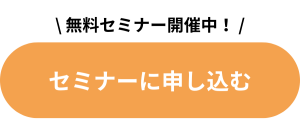マーケティングや商品開発の現場で、生活者の“言葉にならない行動の裏側”を捉える手段として、いま改めて注目されているのが エスノグラフィー(Ethnography) です。
アンケートや定量データだけでは見えてこない、行動の「背景」や「文脈」、そしてその奥にある「価値観」や「感情」を、現場観察やインタビューを通して深く理解することを目的としています。
たとえば、消費者がなぜその商品を「使う」のか、あるいは「使わない」のか──その意思決定の背景には、言葉では説明できない習慣や環境、社会的な圧力、感情の動きが潜んでいます。エスノグラフィーは、こうした“行動の意味”を読み解き、商品開発やUX設計、ブランド戦略などに活かせるインサイトを導き出すための有効な手法です。
本記事では、エスノグラフィーの基本的な考え方から、実際のリサーチ設計・観察・分析のプロセス、そしてビジネス現場への応用方法までを、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
エスノグラフィー調査の概要
定義と目的
「エスノグラフィー調査」とは、生活者の日常生活や使用環境における行動・発話・モノとの関係を観察・記録し、その背景にある価値観や感情、意味構造を読み解く質的リサーチ手法です。調査者が対象者の生活の場(自宅、店舗、職場、移動中など)に入り込み、彼/彼女が「どのように」行動しているかだけでなく、「なぜ」その行動を選んだのかを掘り下げます。
この手法の目的は、単に「どれくらい使われているか」「何人がそうしているか」といった量的データだけでなく、「その行動がどのような文脈で生まれているか」「その行動に潜む価値観や感情は何か」という深い理解を得ることにあります。たとえば、ユーザーがある製品を自宅の入口付近に置くという行動をしていた場合、その単純な「置いている」という事実以上に、「帰宅直後に手を解放したい」「子どもの視線を避けたい」などの意味が隠れている可能性があります。
このような観察・解釈を通じて、商品開発、UX(ユーザーエクスペリエンス)設計、ブランド戦略、サービスデザインなどにおいて、「言われていないニーズ」「隠れた不満」「潜在的な価値」を抽出し、競争優位につなげるインサイトを得ることができます。
社会学・文化人類学にルーツを持つ手法
この手法は、社会学・文化人類学におけるフィールドワーク(現地観察)に起源があります。伝統的には、研究者が特定の社会集団・文化圏に長期間滞在し、生活に密着して観察・参与して、言語・慣習・価値体系を解明するというアプローチです。たとえば、文化人類学者が村落に入り込み、日常生活をともにしながら観察する手法がその典型です。
近年、この「人が暮らす・動く・選択する」というダイナミックな行動を企業活動に応用し、「消費者が製品/サービスを使う現場」をフィールドと捉えることで、マーケティングや製品開発に貢献してきたのが、エスノグラフィー調査です。たとえば、社員が家庭に訪問して生活環境を観察する、または店舗・公共空間で“本当の使われ方”を追うといった企業事例が増えています。
このルーツを知ることは、手法の本質を理解し、適切な設計/実施/分析を行うための土台となります。
なぜエスノグラフィーが注目されているのか
「言葉にならない行動」からインサイトを得る
マーケティング・UX・商品開発の現場では、「ユーザーは何を言ったか」だけでなく「何をしていたか/どう振る舞っていたか」が重要です。多くの場合、ユーザーは自分の行動理由をうまく言語化できないか、あるいは意識せず行動していることがあります。たとえば、「なぜその棚をよく使うのか」「なぜその動線を選ぶのか」など、習慣・無意識・社会的慣性が背景となっている場合があります。
エスノグラフィー調査は、そうした「言葉にならない行動」を丁寧に観察することで、ユーザー自身も気づいていないインサイトを浮かび上がらせます。これによって、製品やサービス設計の方向性を再定義できる可能性があります。
定量データでは見えない“なぜ”を捉える
アンケートやログデータ、アクセス解析などの定量調査は、「どれくらい」「何人」がという傾向を把握するのに有効です。しかし、「なぜその行動をとったのか」「その背景にある価値観は何か」「環境や動線・コンテキストがどう影響しているのか」といった問いにはアプローチが限定されます。
この点で、エスノグラフィー調査は定量では捉えきれない「文脈・環境・習慣・感情」を捉える力を持っています。企業・組織が「ユーザーの声」だけでなく「ユーザーの行動・環境」を理解しようとする流れの中で、注目度を上げています。
特に、製品ライフサイクルが短く、ユーザー体験の差別化が重要な現代において、「行動の背後にある文脈」を掴むことが、マーケティング・UX領域で強みとなっています。
調査の基本構造
観察・記録・解釈の3ステップ
エスノグラフィー調査を進める上では、次の3ステップが基本構造としてしばしば用いられます。
- 1.観察:対象者の行動・環境・発話を現場で観察し、可能なら映像・写真・音声も併用。
- 2.記録:観察の事実(発話、動作、環境状態、相互作用)を詳細に記録する。フィールドノート・動画ログ・画像・音声記録が典型です。
- 3.解釈:記録されたデータから「なぜこの行動が発生したか」「この行動が意味する背景・価値は何か」を整理・分析します。
この3ステップを繰り返し、観察対象の行動パターン・文脈・価値構造を抽出・整理していきます。観察だけで終わらず、「記録 → 解釈」で意味を可視化できる点が重要です。
観察対象の選定と現場入りの手順
観察対象を選定する際には、「典型ユーザー」だけでなく、むしろ「特徴的な行動を持つユーザー」「逸脱しているように見える行動をしているユーザー」を選ぶことで、変化や新しい発見が得やすくなります。また、観察開始前には次のような手順が必要です。
- ・調査目的と観察対象を明確に定義する。
- ・対象者あるいは現場との合意形成(許可・同意取得)を実施する。
- ・研究者の存在が対象者の自然な行動を阻害しないよう、関係づくりを整える。
- ・写真・映像撮影の可否/記録媒体の準備を行う。
- ・観察期間・頻度・タイミング(時間帯・曜日)を設定する。
たとえば家庭内観察の場合、初日は調査者が「見られている」感により対象者が普段と異なる行動をとることがあります。これを「初日フィルター」として傾向から除くこともあるため、観察期間を複数回に分けることが望ましいです。
調査の進め方
① 準備:目的・対象・期間の設定
まずは調査の目的を設定します。例として「なぜあるユーザー層は朝食を抜くのか」「店舗で製品を手に取った後、なぜ買わずに戻すのか」といった具体的な行動に焦点を当てます。目的が曖昧だと観察範囲も曖昧になり、収集データが散漫になります。
次に、観察対象を定義します。例えば「20代後半~30代前半、フルタイム勤務、都心在住、週末は外食中心」など、生活スタイルやセグメントをある程度絞った上で、特徴的な行動を見せる者を選びます。期間・場所(自宅、職場、移動中、店舗)・観察頻度も設定します。
この段階で「観察班・記録手段・倫理同意」「撮影・録音の可否」「データ管理・個人情報保護」などの準備も併せて行う必要があります。
② 現場観察:行動・発話・環境を記録
現場観察では、対象者の発話はもちろんですが、それ以上に「何をしているか」「どこに視線を送っているか」「どのような動線で動くか」「どのようなモノに触れているか」「どんな環境(照明・配置・音・他者)で行動しているか」を観察します。
記録手段としては、フィールドノートをリアルタイムに記述する、あるいは映像・音声を併用して後から分析できるように準備する方法が有効です。特に映像記録を併用すると、「目線・手の動き・微表情」といった細部を後から確認でき、観察漏れを減らせます。
観察中に注意すべきこととして、研究者の存在が対象者の自然な行動を妨げないよう配慮することがあります。たとえば、対象者が「この人に見られている」と意識すると、普段の行動とは異なる振る舞いをするため、観察前に「見守る」関係づくりを行うことが望まれます。
③ 分析:行動文脈と感情の対応関係を整理
現場で記録された大量のデータを整理し、行動→文脈→感情/価値という軸で分析します。たとえば、「夜、寝る前のスマートフォン操作を対象者がしていた」「ベッドに入る直前にSNSをスクロールしていた」という観察があったとします。この行動を「寝る直前のスマホ操作」という行動文脈に置き、「一日の終わりに“繋がり/安心”を確かめたい」という感情の動きを読み取り、「忙しい日常の中で自分を癒やす時間を持ちたい」という価値につながると解釈できます。
このように、行動と環境・発話・表情・モノの相互作用を読み解き、対象者が生活の中でどのような意味を持つ行動をとっているかを抽象化します。分析の際には、複数の観察対象・場面を比較することで共通パターンと例外パターンを浮かび上がらせるとより有効に働きます。
観察時のポイント
研究者バイアスを排除する視点
観察・記録・解釈の過程において、研究者自身の価値観・仮説・過去の経験が分析を歪めるリスクがあります。たとえば、「こういう人はこう行動するだろう」という先入観で観察を進めると、対象者の本当の行動を見落とすことがあります。そのため、仮説は「仮仮説」として保持し、現場データを優先して検証する姿勢が求められます。
また、観察ノートには「事実記述」と「仮説・解釈」を明確に分けて記録することが推奨されます。こうすることで後から他者がレビューしやすくなり、バイアスの可視化・修正が可能になります。
「当たり前」を疑う質問力
対象者の行動の中には、本人も気づいていない“当たり前”が含まれていることがあります。例えば「なぜ冷蔵庫の上にペットボトルを置くのか」「なぜスマートフォンを手放さないのか」こうした一見“当たり前”の行動を丁寧に問い直すことで、新たな気づき(インサイト)が生まれます。
観察時の問いかけとしては、「その行動をする直前/直後には何があったか」「そのモノ・環境との関係は何か」「もしその行動をやめたらどうなるか」といった仮問を立てることで、行動の意味・背景・価値構造を浮き彫りにできます。
データ整理と分析
フィールドノート・映像・写真の扱い方
観察で収集したデータは、まず時間軸や場所軸で整理します。例えば「10月5日 20時 ~ 20時30分/対象者A・自宅リビング・スマホ操作」というように、場面・時間・状況をメタデータとして付与します。映像・写真はその時間軸に紐づけて整理し、後から「何が起きていたか」を正確に再現できるようにします。
フィールドノートには、対象者の行動・発話・モノとの関係・環境条件を「事実」として書き、その後に「気づき/仮説/質問」を別欄に記述します。こうすることで、観察と分析を分離し、レビューしやすくなります。
行動→意味→価値への抽象化プロセス
分析フェーズでは、以下のような段階的抽象化を行います。
- ・行動:対象者が何をしたか(例:「夜に炭酸水を飲む」)
- ・意味:その行動が何を意図/反映しているか(例:「一日の終わりに気分を切り替えたい」)
- ・価値:その意味がどのような価値観・感情に結びつくか(例:「忙しい日常の中で自分をいたわりたい」)
このプロセスによって、単なる行動データを「価値に紐づくインサイト」に変換できます。例えば、製品設計であれば「夜に飲用する炭酸飲料=リセット感を与える」という価値命題を発見し、そこから“持ち運びやすさ”“手軽なリフレッシュ”といった仕様/訴求に繋げられます。
また、分析結果をマトリクス化し、「行動パターン × 感情・価値 × 環境条件」で整理すると、構造的に洞察を整理できます。例として、「週末・仕事後・一人の時間」などの条件で同じ行動が繰り返されているかをチェックします。
他手法との違い
デプスインタビュー・定量調査との比較
- ・デプスインタビュー(深層インタビュー)は、対象者が語る言葉を中心に理解を深めます。つまり、「なぜそのように感じたか」「どのような思考をしたか」を聴く手法です。
- ・一方、エスノグラフィー調査は「行動」を軸にしており、語られない部分(無意識・慣習・文脈)を捉える点が特徴です。観察環境が実際の生活場面であることから、発話だけでは把握できない行動の意味を明らかにできます。
- ・また、定量調査(アンケート・ログ・センサーデータ等)は「どれくらい/何人」がという数値を把握するのに特化していますが、背景や意味構造を深掘りするには限界があります。エスノグラフィー調査は、この定量的な“何”を“なぜ”に結びつける補完的手法として位置づけられます。
n=1分析との補完関係
株式会社デコムが提唱する「n=1分析」は、1人の対象者にフォーカスして深く理解する分析手法です。エスノグラフィー調査は、まさにこのn=1(または少人数)を対象に「行動・環境・価値」を観察するための手段として非常に適しています。
つまり、n=1分析で「この人の価値観・感情」を掘る際のデータベースとして、エスノグラフィー観察が機能すると言えます。行動観察データを起点に、発話データ(デプスインタビュー)や定量データを絡めていくことで、より精緻なインサイトや仮説検証が可能になります。
まとめ
生活者理解の深化とビジネス活用の可能性
エスノグラフィー調査は、生活者の“リアルな行動”を通じて、企業が見落としがちな価値観や課題を可視化する強力な手法です。特に、UX改善、商品/サービス開発、ブランド戦略、顧客体験設計といった分野では、定量データや聞き取りだけでは捕捉しきれない“行動×文脈×価値”を捉えることで、他社との差別化を図るうえでのインサイト源泉となります。
観察を通じて得た「行動の意味」を価値に昇華し、それを起点に設計・戦略を再構築することによって、競争優位性を高めることが可能です。
エスノグラフィーを起点にしたインサイト発見
本稿で紹介した構成──「観察 → 記録 → 解釈」「行動 → 意味 → 価値」──を実践すれば、単なるリサーチではなく、戦略につながる洞察へと昇華できます。さらに、この手法をデプスインタビュー、定量調査、n=1分析などと併用することで、生活者理解の精度を格段に高めることができます。
つまり、エスノグラフィー調査は「見た」「聞いた」「感じた」を統合して“ユーザーの本音”に迫る手段です。そして、そこから見えてくるインサイトこそが、次の企画・開発・戦略の突破口となるのです。
デコムでは、もっと学びたい人に向けて様々なイベントやセミナーを開催しています。
是非、この機会にご参加ください。