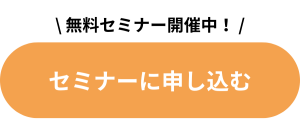アプリやサブスクリプションサービス、ECサイトなど、ユーザーとの関係が長期にわたるビジネスでは、「どのユーザーが」「いつ」「なぜ離脱してしまうのか」を正確に把握することが成果の鍵を握ります。
その行動変化を時間軸で追跡し、継続率(リテンション)改善やLTV向上に役立てる分析手法が コーホート分析(Cohort Analysis) です。
本記事では、コーホート分析の基本概念から、実際の分析手順・可視化方法・活用事例、そしてリテンション戦略への応用までをわかりやすく解説します。継続率改善やデータドリブンな意思決定に取り組む方は、ぜひ参考にしてください。 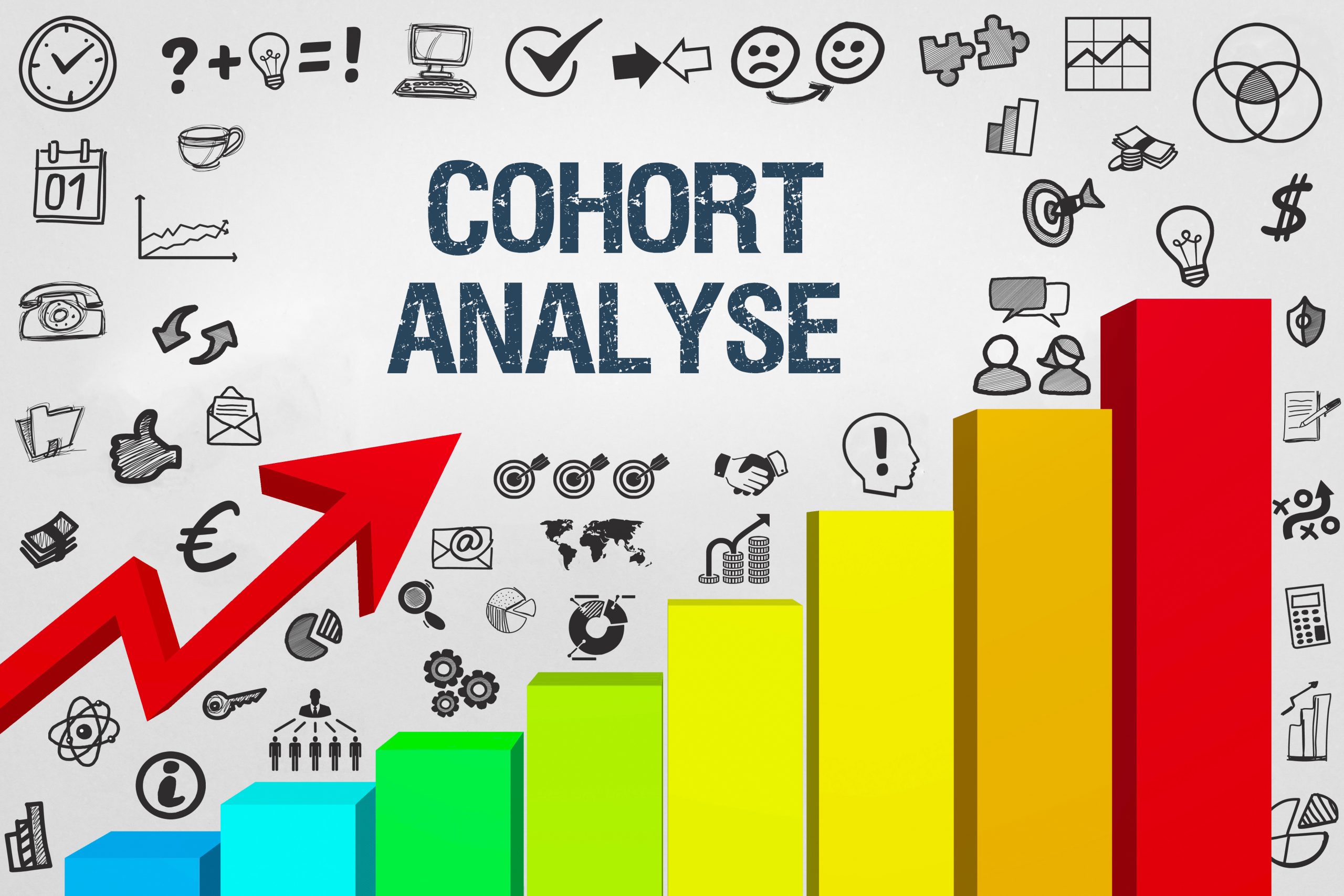
コーホート分析の概要
定義と目的
「コーホート分析(cohort analysis)」とは、共通の属性や起点を持つユーザー群(コーホート)を時間軸で追跡し、その行動変化・離脱・継続パターンを可視化して、マーケティング・プロダクト運営・ユーザー分析に活用する手法です。
例えば、「2024年6月に登録したユーザー」「2024年第1四半期に購入を開始した顧客」「初回体験から7日以内にリピート購入した顧客群」などをコーホートとして設定し、その後の日次・週次・月次で継続率や再購入率、ユーザーあたりの収益(LTV/Lifetime Value)などを追います。
目的としては、主に次のようなものがあります。
- ・ユーザーの離脱(チャーン)や継続のタイミングを把握し、改善ポイントを特定する。
- ・キャンペーンやプロダクト改善・導線変更などの影響を定量的に検証する。
- ・新規獲得/既存ユーザー維持という二つの視点で、どのユーザー群が価値を生んでいるかを明らかにする。
- ・定量データ(ユーザー数・売上)では見えにくい「時間経過による行動変化」「ユーザーのライフサイクル」を捉える。
なぜマーケティングで重要なのか
一般的な集計分析では、月次のユーザー数や売上額の増減ばかりが注目されがちです。しかし、実際に新規登録ユーザーが増えていても、数か月後にはその多くが離脱してしまっていて長期的には伸びていない――というケースがよくあります。ここでコーホート分析を用いることで、「どの登録月のユーザーが何カ月後まで残っているか」「どの時期に獲得したユーザー群がより価値を生んでいるか」を明らかにできます。
特に、サブスクリプションサービス、アプリ運営、ECサイト、SaaS(Software as a Service)など、ユーザーの継続利用が収益に直結するモデルでは、コーホート分析は“継続率改善”および“ライフタイム収益向上”のために不可欠な手法です。
コーホート分析の基本構造
「コーホート」とは何を指すのか
コーホートとは、同じ起点(アクション開始日、登録日、購入日など)や同じ特徴(初回利用者、特定チャネル経由、特定プラン加入など)を共有するユーザー群を指します。
重要なのは、コーホート形成後、原則としてそのコーホートに新たなメンバーが追加されない「固定プール型(static pool)」にする点です。これにより、時間経過による変化を純粋に観察できます。
分析の軸:取得日/購入日/利用開始日
コーホート分析では、どの起点を“コーホート開始点”として設定するかが重要です。典型的には以下のような軸があります:
- ・取得コーホート(登録/DL起点):ユーザーがサービスを登録/アプリをダウンロードした日を起点とする。
- ・行動コーホート(購入・初回利用起点):初回購入日時、初めて機能を使った日時などを起点とする。
このような起点を設定したうえで、日次、週次、月次などの時間軸で、継続率・再利用率・平均購入額などを追跡します。
例えば「2024年1月登録ユーザー」のコーホートを作り、登録から1カ月後、3カ月後、6カ月後の継続状況を比較することで、どの導線や獲得チャネルが“長期価値のあるユーザー”を生み出しているかが見えてきます。
分析の手順
① コーホートを設定する(例:登録月ごと)
分析を始める前に、目的に応じたコーホートを明確に設定します。例えば:
- ・登録月別(例:2024年5月登録、2024年6月登録)
- ・チャネル別+登録月(例:広告A経由で2024年6月登録)
- ・初回購入月別/初回アクション月別(例:2024年7月に初購入)
コーホートを設定したら、そのコーホートに含まれるユーザー数、起点日をマークし、後続期間の追跡対象とします。
② 指標を選ぶ(例:継続率・LTV・再購入率)
追跡する指標は、目的によって変わりますが、典型的なものを挙げると以下の通りです:
- ・継続率(リテンション率):コーホートユーザーが一定期間後にサービスを利用/活動を継続している割合。
- ・解約率(チャーン率):継続していたユーザーが離脱した割合。
- ・再購入率/リピート率:コーホート内ユーザーのうち再び購入等を行った割合。
- ・LTV(ライフタイムバリュー):コーホートユーザーが生涯にわたってどれだけ収益をもたらしたか。
適切な指標を選び、時間経過(例:登録月+1カ月、+3カ月、+6カ月)で変化を追いましょう。
③ 表に可視化して傾向を読む
コーホート分析では、データを表形式やヒートマップ形式で可視化することが効果的です。たとえば、行(コーホート開始月)×列(起点からの月数)というマトリクスを作り、セルに継続率や再購入率を入れていきます。さらに色付け(ヒートマップ)により、どのコーホート/どの時期で離脱が多いか、どの時期で優秀ユーザーが残っているかを一目で把握できます。
このように「どの獲得月のユーザー群が3カ月後も残っているか」「ある月に離脱が急増しているか」などを可視化し、改善すべきタイミングやチャネルを発見できます。
コーホート分析の種類
取得コーホート(登録・DL起点)
取得コーホートは、ユーザーがサービス登録・アプリダウンロード・会員登録などを行った“起点日”を基にグループ化します。このコーホートでは、登録直後の導入/オンボーディング体験の影響を長期的に見ることができます。例えば、登録から1日目、7日目、30日目での継続率を比較し、どの登録月が質の高いユーザーを獲得しているかを確認できます。
行動コーホート(購入・利用行動起点)
行動コーホートは、ユーザーの“重要な行動”を起点にして設定します。例えば「初回購入」「初回アプリ利用」「特定機能初使用」などです。このタイプのコーホートは、ユーザーが価値を感じる行動をいつ取るか、またその後どう継続していくかを観察するのに有効です。たとえば、初回購入から1カ月後の再購入率や3カ月後の平均購入額を比較することで、行動起点でどのセグメントがより価値を生んでいるかを把握できます。
実践例
例① サブスクサービスの継続率分析
ある定額制動画配信サービスでは、2023年7月・8月・9月に登録を開始したユーザー群をコーホートとし、登録翌月、登録3カ月後、登録6カ月後の継続率を比較しました。
- ・7月登録コーホート:翌月継続率 80%、3カ月後 55%、6カ月後 38%
- ・8月登録コーホート:翌月継続率 78%、3カ月後 52%、6カ月後 34%
- ・9月登録コーホート:翌月継続率 82%、3カ月後 60%、6カ月後 46%
この分析を通じて「9月登録ユーザーの継続率が他と比較して高い」ことが判明し、9月獲得キャンペーン(無料体験期間延長+紹介特典)が継続率向上に寄与していた可能性が見えてきました。これをもとに、7月・8月のキャンペーン設計を再検討し、オンボーディング導線の改善が行われました。
例② ECサイトのリピート購入分析
あるEC事業者では、2024年1月、2月、3月に初回購入した顧客をコーホート化し、初回購入後1カ月・3カ月・6カ月の再購入率を追いました。
- ・1月初回購入コーホート:1カ月後再購入率 25%、3カ月後 14%、6カ月後 7%
- ・2月初回購入コーホート:1カ月後再購入率 22%、3カ月後 12%、6カ月後 5%
- ・3月初回購入コーホート:1カ月後再購入率 28%、3カ月後 18%、6カ月後 12%
この結果から、3月購入顧客群のリピート率が相対的に高かったため、どのチャネル経由・どの販促施策がこの群に効いていたかを分析。さらにオンサイト/メール/広告の組み合わせを見直して、初回購入翌月のリピート率改善施策に繋げました。
グラフの見方
ヒートマップで離脱ポイントを把握
コーホート分析を可視化する際、ヒートマップ形式は非常に効果的です。行がコーホート(登録月など)、列が起点からの月数で、セルに継続率・再購入率などを入れて色を付けていきます。例えば、色が徐々に薄くなっていくコーホートがあれば、そのタイミングで離脱が起きている可能性があります。「登録から2カ月目に色が一気に薄くなっている」場合、オンボーディングの失敗や導線設計の課題が考えられます。
残存率曲線(リテンションカーブ)の読み方
残存率曲線(またはリテンションカーブ)は、あるコーホートの継続率を時間軸でプロットしたグラフです。横軸が時間(例:登録からの週数/月数)、縦軸が継続率(%)です。理想的には緩やかな傾きで下がる曲線ですが、急激に下がる場面があれば改善余地があります。また、複数コーホートを重ねて比較すれば、どのコーホートが“優秀”か、また“どのタイミングで差が出ているか”が分かります。分析者はこのカーブをもとに「どの期間で離脱が集中しているか」「どの改善が効果を出しているか」を読み取ります。
活用のポイント
顧客セグメントごとの課題発見
コーホート分析では、登録月別・チャネル別・プラン別・地域別などと切り分けて分析することで、どのセグメントに課題があるかが浮き彫りになります。例えば「広告キャンペーン経由のユーザーが3カ月後の継続率が低い」なら、そのチャネル出稿・オンボーディング導線・初回体験に改善余地があると判断できます。
キャンペーン効果の比較検証
新たなキャンペーンを実施した後、キャンペーン実施月のユーザーをコーホートとして設定し、その後継続率や再購入率を他月と比較することで「このキャンペーンが本当に長期価値向上に寄与したか」を検証できます。これにより、短期効果(登録数)だけでなく、長期効果(残存・収益)を見据えた意思決定が可能になります。
コーホート分析と他手法の違い
リテンション分析・RFM分析との比較
- ・リテンション分析:通常、登録ユーザーが何日後/何カ月後に再使用しているかを追う指標であり、コーホート分析と重なる部分があります。ただし、リテンション分析は全ユーザーを対象に一律で追うことが多く、どの獲得チャネル/どの登録月が優れているかというコーホート別比較までは踏み込まないことがあります。
- ・RFM分析(Recency, Frequency, Monetary):顧客を「直近購入日」「頻度」「金額」で分類し価値の高いセグメントを見つける手法です。こちらは“ある時点の顧客価値”の把握に優れますが、時間経過による継続・離脱の変化を捉える点ではコーホート分析が優れています。
コーホート分析は、これら既存手法を補完し、特に“時間軸での行動変化”にフォーカスする点が特徴です。
組み合わせで得られる洞察
最も強力な分析は、コーホート分析+RFM分析+リテンション分析を組み合わせることです。例えば、コーホート分析で「ある登録月のユーザー群が3カ月後に離脱が多い」ことが分かったら、その群をRFM分析で「その群の頻度・金額傾向」を確認し、更に定性分析(ユーザーインタビュー)で「なぜ離脱が起きたか」を深掘りするといった流れが有効です。こうして「どの登録月」「どのチャネル」「どのユーザー層」が長期価値を生むかを精緻に把握できます。
まとめ
コーホート分析の価値と限界
コーホート分析は、単なる集計データでは見えない「時間経過によるユーザー行動の変化」「獲得チャネルや登録月別の継続傾向」「離脱ポイント」を可視化できる点で、リテンション改善・ユーザー価値向上に非常に有効な手法です。一方で、いくつかの限界もあります。
- ・コーホートを形成してから一定期間(例:3カ月、6カ月)を待たねば有効なデータが出にくい。
- ・小規模ユーザー群では統計的に信頼しにくい。
- ・起点の定義や切り口が適切でないと、意味の薄い分析になりがち。
これらを認識した上で、適切な設計・解釈・改善アクションにつなげることが重要です。
データドリブンな改善への次の一歩
コーホート分析を社内で定常的なプロセスに落とし込むことで、新規獲得施策だけでなく、「登録直後の導入」「1カ月後の継続」「3カ月後のリピート」「6カ月後のLTV」というライフサイクル全体に向けた改善設計が可能になります。さらに、分析結果から導き出された仮説をA/Bテストや機械学習モデルによって検証し、KPI/OKRと紐づけることで、より体系的なデータドリブン改善への流れが作れます。
ぜひ、まずは「過去3〜6カ月分の登録ユーザーをコーホート化して追跡する」ところから始めてみてください。そして、観察された傾向をもとに「登録翌月に離脱が多い」「特定チャネルの登録ユーザーが3カ月後に残りにくい」などの課題仮説を立て、改善施策を実施し、次のコーホートで成果を測定しましょう。
デコムでは、もっと学びたい人に向けて様々なイベントやセミナーを開催しています。
是非、この機会にご参加ください。