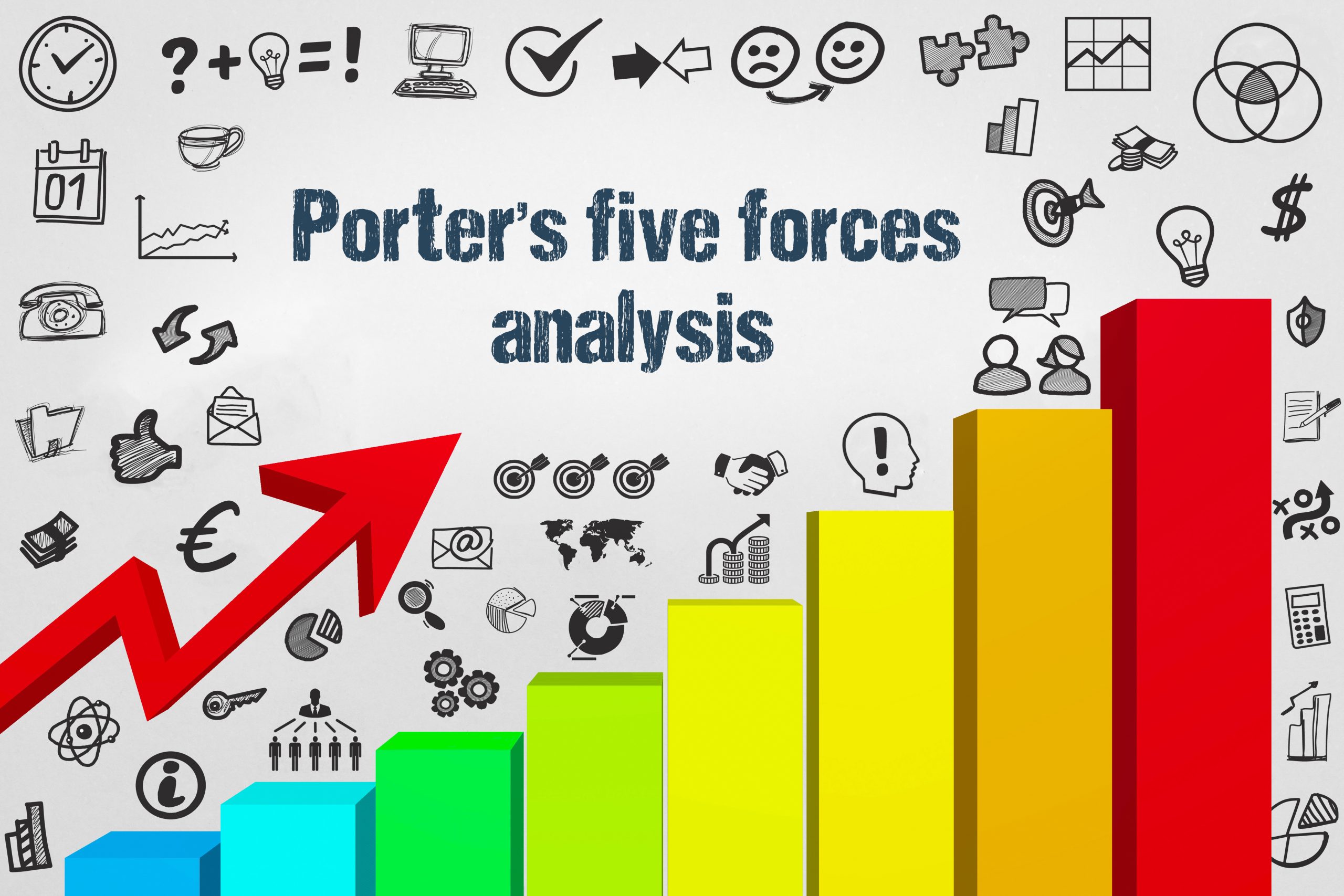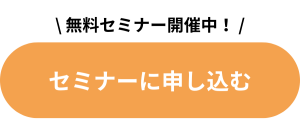本記事では、5F分析(5フォース分析)の基本的な定義から、5つの競争要因(既存競合・新規参入・代替品・売り手・買い手)の詳細解説、実施手順、他フレームワークとの連携方法、具体的な業界での活用事例までをご紹介します。
5F分析(5フォース分析)とは?
フレームワークの定義と起源
5F分析(Five Forces Analysis)とは、ハーバード大学のマイケル・E・ポーター教授によって提唱された業界構造分析のフレームワークです。業界における競争環境を「5つの競争要因」に分解し、それぞれの影響度を評価することで、企業がどのように競争優位を築くべきかを導き出します。
なぜ今、5F分析が注目されているのか
現代の市場はデジタル化やグローバル化により変化のスピードが加速しています。新規プレイヤーの参入や代替手段の多様化により、業界構造が流動的になっており、定量的な競争分析の必要性がますます高まっています。5F分析は、こうした複雑な業界環境の中で構造的な理解を深めるための有効な手段となり得るので注目されているのです。
5つの競争要因の解説
5F分析にて分析要素となる競争要因は以下の5つです。
① 業界内の競合関係(既存競合の脅威)
市場内で既に活動している競合他社との競争の激しさです。プレイヤー数、成長率、固定費の大きさ、差別化の程度などが影響し、競争が激しいほど利益率が低下する傾向があります。
② 新規参入の脅威
新たに市場に参入しようとする企業がもたらす競争圧力です。参入障壁(規制、初期投資、ブランド力、流通網など)が低い業界では、新規プレイヤーの影響で価格競争が起きやすくなります。
③ 代替品の脅威
顧客のニーズを満たす他の手段や製品による圧力です。たとえば、映画館にとってのストリーミングサービスのように、異なる業界からも代替品は出現し得ます。
④ 売り手(供給企業)の交渉力
原材料や部品などを供給する業者の交渉力が高いと、価格や取引条件で不利になりやすく、収益性に影響します。供給業者の数が少ない、代替手段がない場合は特に注意が必要です。
⑤ 買い手(顧客)の交渉力
顧客が情報を持ち、選択肢が豊富な場合には、価格交渉力が強くなり、利益圧迫要因となります。特にBtoB取引では、大口顧客の影響が大きくなりがちです。
5F分析を活用するメリット
5F分析を活用することで、以下のようなメリットを得ることができます。
業界構造の理解によるリスクの可視化
業界の構造的なリスク(例:過当競争、代替技術の登場)を事前に把握できるため、戦略策定時のリスク管理に役立ちます。
競争優位を築くための戦略的判断材料
各要因の強さを分析することで、自社がどこにリソースを集中すべきか(差別化、コスト競争力など)を判断しやすくなります。
他フレームワークとの併用でより精度の高い戦略立案が可能
SWOTや3C分析と組み合わせることで、より立体的な戦略構築が可能になります。例えば、5F分析で業界構造を把握し、SWOTで自社の立ち位置を明確にするなどの連携が有効です。
5F分析の実施手順とポイント
-
分析対象(業界・市場)の明確化
まず、どの業界・市場を対象に分析するのかを明確にします。境界が曖昧な場合は、製品カテゴリや顧客層ごとに分けて分析する必要があります。
参考記事:市場調査とは何か:求められているニーズを顕在化する手軽な手法
-
情報収集と整理のコツ
公開情報(業界団体、決算資料、政府統計など)を活用し、できるだけ客観的なデータを集めることが重要です。また、社内の営業部門や顧客ヒアリングからの一次情報も有効です。
-
SWOT・STP・3Cなど他のフレームワークとの連携活用法
3C(Customer, Competitor, Company)との組み合わせで、市場の魅力と自社のポジショニングを両面から検討できます。STPでターゲティングとポジショニングを明確にし、5Fで競争状況を補完するアプローチも効果的です。
5F分析を成功させるための注意点
5F分析には注意点もあります。成功させるためにも注意深く分析しましょう。
主觀的評価に頼らず客観的データで補強する
業界や競合に関する思い込みで判断すると、誤った戦略につながります。複数の情報源を活用し、定量的な裏付けを取りながら評価することが大切です。
市場変化に対応し定期的に見直すことの重要性
5F分析は一度実施して終わりではなく、市場や競合環境の変化に応じて見直す必要があります。特にテクノロジー業界など変化の早い業界では、半年から1年ごとのアップデートが推奨されます。
活用事例:5F分析で見える業界戦略
ここでは5F分析の活用事例を紹介します。是非自身に当てはめてみて分析にご活用下さい。
BtoC業界(例:飲食・小売)の競争構造分析
BtoC業界では、特に飲食や小売のような日常的に接する業界において、5F分析が競争環境を理解する上で有効に機能します。たとえば飲食業界では、ウーバーイーツや出前館などのデリバリーサービスが急速に普及したことで、新規プレイヤーの参入が容易になり、「新規参入の脅威」が増大しています。これに伴い、自社店舗の集客力や差別化が問われるようになりました。
さらに、「代替品の脅威」としては、コンビニやスーパーで手に入る冷凍食品やレトルト商品の品質が年々向上しており、外食の代替手段として支持を集めています。「売り手の交渉力」では、特定のブランドや産地に依存する食材の場合、供給業者側が価格や納期の交渉で優位に立つこともあります。一方、「買い手の交渉力」は非常に高く、SNSやレビューサイトの普及により、顧客の評価が即時に広がるため、価格や品質、接客対応のいずれかが満たされない場合、簡単に顧客離れが起こる可能性があります。
このように、飲食・小売業界は、5つの力が複雑に絡み合う中で継続的なイノベーションと顧客接点の強化が求められます。
BtoB業界(例:IT・製造)の参入障壁と競合戦略
BtoB業界、特にITや製造業においても5F分析は有効です。たとえばIT業界では、クラウドサービスやAI関連技術の進化により多くの新興企業が参入していますが、一方で高いセキュリティ要件や、既存システムとの連携などが「新規参入の障壁」となっています。また、「業界内の競争」は激化しており、特にSaaS業界では低価格・無料プランによる顧客獲得競争が続いています。
「買い手の交渉力」も高まりつつあり、ITに明るい企業担当者が増えたことで、複数のベンダーを比較し、コスト・機能・導入実績を厳しく見極める傾向が強まっています。また、製造業においては、品質保証や特許取得などが「参入障壁」となり得る一方で、材料費やエネルギーコストの変動により「売り手の交渉力」が強くなる場面もあります。
これらの分析をもとに、BtoB企業は「技術力の差別化」や「特定業界への特化」など、自社の強みを活かしたポジショニング戦略を設計することが可能になります。
まとめ
5F分析は、業界を構造的に捉え、戦略立案における出発点となる重要なツールです。競争要因を把握することで、どこに機会があり、どこに注意が必要かが明確になります。
主観的な印象だけでなく、定量データを活用して客観性を担保することが、より実践的な戦略に結びつきます。またフレームワークとの組み合わせにより、精度と実行力の高い意思決定が可能になります。ぜひ読者の皆さんもこの記事を参考にして5F分析を行い、自身の事業を成功に導いて下さると幸いです。
デコムでは、もっと学びたい人に向けて様々なイベントやセミナーを開催しています。
是非、この機会にご参加ください。